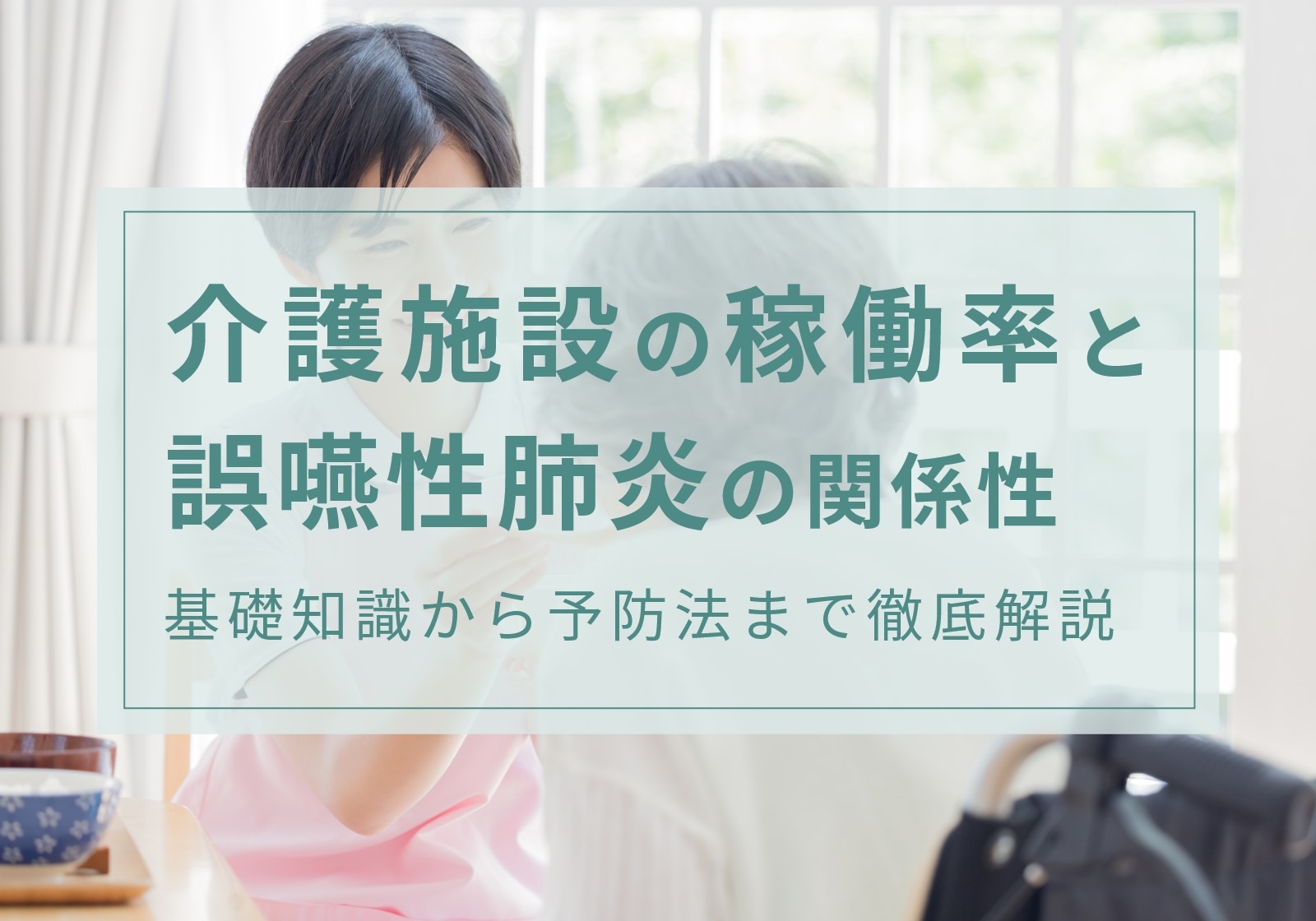
介護施設の稼働率を左右する誤嚥性肺炎|経営安定につながる予防策を解説
「介護施設の稼働率を上げるため、誤嚥性肺炎との関連を知って対策したい」と考えている方もいるでしょう。
誤嚥性肺炎の発生によって利用者が入院・死亡してしまうと空床となり、介護施設の稼働率の低下につながります。
稼働率を向上するためには、予防策を実施して施設内の誤嚥性肺炎の発生件数をどれだけ減らせるかが重要なポイントです。
この記事では、誤嚥性肺炎が稼働率低下につながる理由や明日からできる誤嚥性肺炎の予防策について分かりやすく解説します。
記事を読んで、稼働率を向上するための誤嚥性肺炎への対策について詳しく知り、安定した施設経営のために明日から早速試してみましょう。
1章:介護施設の稼働率を左右する誤嚥性肺炎対策の重要性
ここでは、介護施設における稼働率の考え方と、誤嚥性肺炎がどのように稼働率に影響を及ぼすのか、その対策の重要性について解説します。
1-1:介護施設における稼働率とは?
介護施設における稼働率とは、施設の定員数に対して、実際に入居している利用者の割合を示す指標です。多くの介護施設では、稼働率は月単位で管理しています。
稼働率の具体的な式は以下のとおりです。
稼働率=1ヶ月の延べ利用者数 ÷ (1ヶ月の営業日数×1日の利用定員数)× 100 |
例えば、1日の利用定員数が100名の介護施設において、1ヶ月の延べ利用者数が2,850名、1ヶ月の営業日数が30日だった場合の稼働率は、単純に計算すると95%となります。
東京都高齢者福祉施設協議会が令和6年1月に報告した「東京都内の特別養護老人ホーム入所(居)待機者に関する実態調査」のなかで、回答者(特養)の令和4年度における全体の平均稼働率は92.02%でした。令和3年度の同報告での全体の平均稼働率は93.50%で、1.48%低下しています。
このように、稼働率は施設の経営状態を客観的に把握できる数値の1つです。
稼働率が高ければ、施設は安定した収益を得られるため、質の高いサービス提供の継続につながります。しかし、低い場合は経営への影響が考えられるため、一刻も早く対策をとるのがよいでしょう。
1-2:誤嚥性肺炎が稼働率低下につながる理由
誤嚥性肺炎が稼働率低下につながる理由は、以下の2つです。
- 入院による一時的な空床が発生するから
- 施設の評判・イメージへの悪影響があるから
それぞれ解説します。
1-2-1:入院による一時的な空床が発生するから
誤嚥性肺炎が稼働率低下につながる理由として、既存入居者における一時的なベッドの空きが発生することが挙げられます。入院した利用者の家族からの同意があれば、ショートステイとして空いたベッドを埋められますが、もし利用がない場合、短期的な空床が施設の稼働率に影響を与えてしまいます。
特に、誤嚥性肺炎は高齢者の場合、再発が多いため、入退院による既存入居者の出入りが頻繁に起こることで、スタッフの調整による負担が増えてしまうのが問題です。
これが複数ケース発生すると、施設の経営にも影響が出かねません。
1-2-2:施設の評判・イメージへの悪影響があるから
誤嚥性肺炎が稼働率低下につながる理由として、施設の評判・イメージへの悪影響があることも考えられます。
誤嚥性肺炎は、「不顕性誤嚥」といって、明らかな誤嚥事故がなくても起こる場合があります。例えば、就寝中に食道からの逆流や唾液などを誤嚥した時などです。しかし、施設内での誤嚥による肺炎であれば、家族などからの信頼を失うこともあるでしょう。
利用者やその家族からの訴訟などによって、事故の概要が知れ渡った場合、施設に対するイメージが悪くなる可能性もあります。
施設は地域住民の利用が多いため、誤嚥事故が多いという情報が外部に漏れれば、「あの施設は管理体制が不十分ではないか」というネガティブな印象が広がるかもしれません。
結果として新規の入居希望者の減少につながり、稼働率の低下を招く要因ともなり得ます。
1-3:誤嚥性肺炎発生によるコスト増と経営への影響
誤嚥性肺炎の発生による経営への影響は、稼働率低下による収入減だけではありません。コスト増も引き起こし、施設経営全体に負担をかけます。
例えば、施設サービス事業者の場合、医療費や発症した入居者への対応が主なものです。医療機関との連携や家族への説明など、通常業務に加えてスタッフの労力を必要とします。
また、スタッフの負担増による離職リスクや、施設の評判低下による損失も考えられます。
1-4:稼働率と介護報酬・加算
介護施設の経営を考えるうえで、稼働率と介護報酬・加算の関連を理解することは重要です。稼働率が低ければ、介護報酬や加算も得られなくなり、施設全体の収入は減少してしまいます。
一方で、誤嚥性肺炎予防に積極的に取り組むと、特定の介護報酬加算の算定につながる可能性があります。
施設サービスであれば、口からの栄養摂取が難しい入所者に対して多職種アプローチをおこなう経口維持加算、居宅サービスでは口腔連携強化加算などが主な例です。各加算の算定要件を確認したうえで「算定できる加算がないか」「新たに加算を算定するためには何が必要なのか」を考えてみましょう。
算定要件をクリアできれば、利用者の「食べる楽しみ」とQOL(生活の質)向上を支援しながら、収入増も期待できます。
居宅サービスにおける口腔連携強化加算の概要・算定要件については、以下の記事で詳しく解説しています。経営のために加算について把握しておきたいという方はぜひご覧ください。
オススメ記事:【2024年報酬改定で新設】口腔連携強化加算の算定要件と注意点を解説
2章:チェックしておきたい誤嚥性肺炎の基礎知識
ここでは、介護施設の稼働率アップにつなげるため、誤嚥性肺炎の基礎知識について解説します。
2-1:誤嚥性肺炎とは?
誤嚥性肺炎とは、食べ物や飲み物、あるいは唾液などが誤って気管に入り、それに含まれる細菌が肺の中で炎症を引き起こす病気です。
通常、私たちが飲み込んだものは食道を通って胃に運ばれますが、飲み込む力(嚥下機能)が低下していると、気管の方へ流れ込んでしまう場合があります。
特に高齢者は、加齢や持病の影響で嚥下機能が弱まっている場合が多いため、注意が必要です。
2-2:介護施設で特に注意すべき誤嚥性肺炎のリスク
加齢や基礎疾患により嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎のリスクが高い高齢者が集団で生活する場が介護施設です。
介護施設の場合は特に、1対1で対応できない状況が生まれることが非常に高いリスクでしょう。
誤嚥事故を防ぎながら個人に合わせたケアを提供するため、見守りの徹底や声かけなど、細やかな注意が求められます。
2-3:誤嚥が疑われるサイン・症状
誤嚥性肺炎を予防するためには、誤嚥の兆候を早期に発見することが重要です。
発熱や咳、痰などの肺炎の典型的な症状に加え、元気や食欲がないなどの不調に陥る場合もあります。
高齢者の場合は、はっきりとしたむせがない不顕性誤嚥も多く見られます。不顕性誤嚥は就寝中にも起きやすいため、胃からの食物逆流を起こしやすい方は特に、食後2時間は横にならない・就寝時にベッドの上半身側を少しだけ上げておくなどの対策が必要です。
3章:稼働率向上のために明日からできる誤嚥性肺炎の予防策
稼働率向上のために明日からできる誤嚥性肺炎の予防策は、以下の4つです。
- 口腔ケアを適切におこなう
- 安全な食事介助を心がける
- 嚥下機能の評価を定期的におこなう
- スタッフの教育・研修体制をつくる
それぞれ説明します。
3-1:口腔ケアを適切におこなう
誤嚥性肺炎予防において、口腔ケアを適切におこなうことは効果的な手段の1つです。口腔内を清潔に保つことで、万が一誤嚥した場合でも肺へ侵入する細菌の量を少なくし、肺炎発症のリスクを減らせます。
口腔ケアの基本的な流れは以下のとおりです。
手順 | 項目 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
① | 声かけをする | 声をかけてから準備を始める。リハビリの観点からも、本人が可能であれば体位の変更や口の開閉などを依頼する。 |
② | 体位を整える | あごを適度に引き、座位や半座位に整える。口腔ケアのときにも、ブラッシング後の汚れを誤嚥する可能性もあるため、誤嚥しにくい姿勢が大切。 |
③ | 口腔内を観察する | 歯や歯ぐきの状態を確認する。口内炎や出血など、口腔内の異常がないかどうかも重要な観察ポイント。 |
④ | 口腔ケアを実施する | 歯ブラシを使い分け、歯や歯の間、歯ぐき、舌、上あご・頬の内側などを丁寧に清掃する。義歯の清掃も毎食後におこなうのがよい。清掃後はうがいをして口腔内の汚れをすべて出す。うがいができない場合は、口腔用のウエットティッシュなどで汚れをふき取る。 |
効果的なケアをおこなうためには、日々の口腔ケアを実施する前に口腔状態を観察・評価することが特に重要です。
観察や評価の際に、歯や歯ぐきなどの口腔内の異常や義歯の不具合を発見した場合、早期に歯科介入につなげられるからです。
そのため、日常的に適切な口腔ケアをおこない、観察や評価を継続することで、口腔トラブルを早期に発見でき、重症化防止につながります。
毎食後の歯磨きやうがい、義歯の清掃、舌苔の除去など、入居者の状態に合わせた適切な方法で口腔ケアを実施しましょう。
誤嚥性肺炎の予防に口腔ケアが必要な理由や、具体的な手順については以下の2記事で分かりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。
オススメ記事:誤嚥性肺炎の予防に口腔ケアはなぜ必要?得られる効果や手順も解説
オススメ記事:【介護現場向け】口腔ケアの具体的な手順・歯科連携の方法を徹底解説
3-2:安全な食事介助を心がける
誤嚥性肺炎を防ぐためには、よりよい食事介助の方法に見直すなどして安全な対応を心がけることが不可欠です。入居者の嚥下機能に合わせて食事の形態を変えて提供しましょう。
食事の際は、体幹をまっすぐに保ち、やや前傾であごを少し引いた「飲み込みやすい姿勢」が基本です。
また、食事に集中できるような静かで落ち着いた環境を整えましょう。スタッフは入居者の飲み込みを一口ずつ確認しながら介助をおこなうことが重要です。飲み込みができず、口の中に食べ物が溜まっていくことがないように見守りましょう。
3-3:嚥下機能の評価を定期的におこなう
誤嚥性肺炎を効果的に予防するには、入居者の嚥下機能を定期的に評価し、状態に合わせたケアを提供することが大切です。
日常的な評価は、食事中のむせや食事時間、声の変化などを介護・看護スタッフが観察し記録します。
介護・看護スタッフがおこなう、嚥下機能を評価するスクリーニングテストの例は以下のとおりです。
テスト名 | 具体的な方法 |
|---|---|
反復唾液嚥下テスト | 30秒間に何回唾液を飲み込めるかによって嚥下機能を評価する。平均が6回程度。 |
改訂水飲みテスト | スプーン1杯分(3ml)の冷水を口に含んで嚥下することで嚥下機能を評価する。むせないか・呼吸が問題なく行われているか・声の変化がないかを確認する。 |
フードテスト | 入居者にとって飲み込みやすい食物を使っておこなう。使用される食物はプリンやゼリーなど。 |
スクリーニングテストにおいてリスクが高いと判断された場合や、誤嚥のサインが頻繁に見られる場合は、速やかに医師や歯科医師、言語聴聴士などの専門職と連携し、対応しましょう。
施設サービス・居宅サービスのどちらにおいても、介護・看護スタッフによる適切な嚥下機能の評価が重要な役割を果たします。
日常のケア担当のスタッフによる評価に基づいた個別ケアによって、誤嚥リスクを減らすことにつながります。
アサヒグループでは、介護現場での口腔評価が専門的で難しく、対応する時間が取れないと感じている介護事業者様に向けて、口腔内評価アプリ「クチミル」をご紹介しています。
「クチミル」なら、スタッフ様がスマートフォンで口腔動画と簡単な問診情報を当社に送付いただくだけで、口腔内の知識に詳しい専門スタッフによる評価が可能です。
無料でお問い合わせ・資料請求ができますので、興味のある事業者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。
リリースキャンペーン実施中!
\ 初期導入費用が今だけ「0円」 /
3-4:スタッフの教育・研修体制をつくる
誤嚥性肺炎の予防策を施設全体で効果的に実施するためには、スタッフの教育・研修体制をつくることが必要です。
基礎知識や口腔ケアの具体的な方法、安全な食事介助の方法などについて、定期的な研修や勉強会を実施しましょう。歯科専門職に研修を依頼するのも効果的です。
スタッフの意識が高まり、知識が身につくことで、口腔内トラブルや誤嚥のサインに早期に気づきやすくなります。
4章:稼働率向上と誤嚥性肺炎予防を両立するための考え方
介護施設の稼働率向上と誤嚥性肺炎の予防は関連しており、2つを両立させる視点を持つことで、安定した施設経営の実現につながります。
稼働率向上と誤嚥性肺炎の予防を確立するための考え方は、以下の3つです。
- 経営安定は安全管理体制から生まれると考える
- 業務負担とケアの質のバランスを考える
- 利用者のQOLを考えたサービスづくりをめざす
それぞれ説明します。
4-1:経営安定は安全管理体制から生まれると考える
稼働率向上と誤嚥性肺炎の予防を確立するための考え方の1つ目は、経営安定は安全管理体制から生まれると考えることです。
介護施設における安全管理体制の整備は、誤嚥性肺炎を含む入居中の事故を予防し、入居者が安心して生活できる環境づくりのポイントの1つです。
誤嚥性肺炎の予防策はコストや人件費がかかるため、遠回りなのではないかと思えるでしょう。しかし、この安全管理体制の整備こそが、施設の経営安定につながる方法です。
誤嚥性肺炎の予防に積極的に取り組むことで、入居者の入院リスクを減らし、結果として稼働率の維持や向上をめざせます。
4-2:業務負担とケアの質のバランスを考える
2つ目の考え方は、業務負担とケアの質のバランスを考えることです。
誤嚥性肺炎の予防策を強化すると、一時的にスタッフの業務負担が増えると感じるかもしれません。
しかし、長期的に見れば、日々の口腔ケアにより誤嚥性肺炎を予防でき、結果として稼働率が上がるという、よい循環を生み出します。
予防策を導入する際は、スタッフが無理なく継続できる仕組みづくりを意識し、多職種連携も活用しましょう。
4-3:利用者のQOL向上という視点を持つ
介護施設の運営において、稼働率や誤嚥性肺炎の予防という観点のほかに、入居者のQOL向上という視点を持つことも大切です。
「誤嚥を防ぐために、経口摂取をやめる」という消極的な選択ではなく、「どうしたら安全に、楽しく食事を続けられるか」という視点が求められます。
口腔ケアや利用者に合った食事形態の見直しなど、専門職の評価にもとづいた利用者本位のサービスに立ち返ることで、誤嚥性肺炎の予防につながり、結果として稼働率の向上をめざせるでしょう。
まとめ:介護施設の稼働率を上げるには誤嚥性肺炎の予防が不可欠
稼働率向上のために明日からできる誤嚥性肺炎の予防策は、以下の4つです。
- 口腔ケアを適切におこなう
- 安全な食事介助を心がける
- 嚥下機能の評価を定期的におこなう
- スタッフの教育・研修体制をつくる
介護施設の安定した運営と質の高いケア提供をめざすうえで、誤嚥性肺炎の予防は不可欠だといえます。誤嚥性肺炎の発生は、入居者の健康だけではなく、介護施設の稼働率低下やコスト増など、経営面にも深刻な影響をおよぼすからです。
これらの予防策は、稼働率向上に即効性のある方法とは言い切れません。しかし、明日からすぐに取り組んでいけば、誤嚥性肺炎の発生リスクを回避できるだけではなく、入居者のQOL向上や施設への信頼構築にもつながります。その結果、安定した稼働率の維持、向上が期待できるでしょう。
アサヒグループでは、介護現場での口腔ケアが専門的で難しい・スタッフ教育の時間が足りないと感じている介護事業者様に向けて、口腔内評価アプリ「クチミル」をご紹介しています。
「クチミル」は、スタッフ様がスマートフォンで口腔動画と簡単な問診情報を当社に送付いただくだけで、口腔内の豊富な知識をもった専門職員による評価ができるサービスです。
東京科学大学大学院(旧東京医科歯科大学大学院)の松尾浩一郎教授が監修しており、信頼できる情報をもとに作成しているため、安心してお申し込みいただけます。
お問い合わせ・資料請求は無料です。ぜひ、以下よりお問い合わせください。
リリースキャンペーン実施中!
\ 初期導入費用が今だけ「0円」 /
【参考資料】
令和5年度 東京都内特別養護老人ホーム入所(居)待機者に関する実態調査|東京都社会福祉協議会 東京都高齢者福祉施設協議会 制度検討委員会


